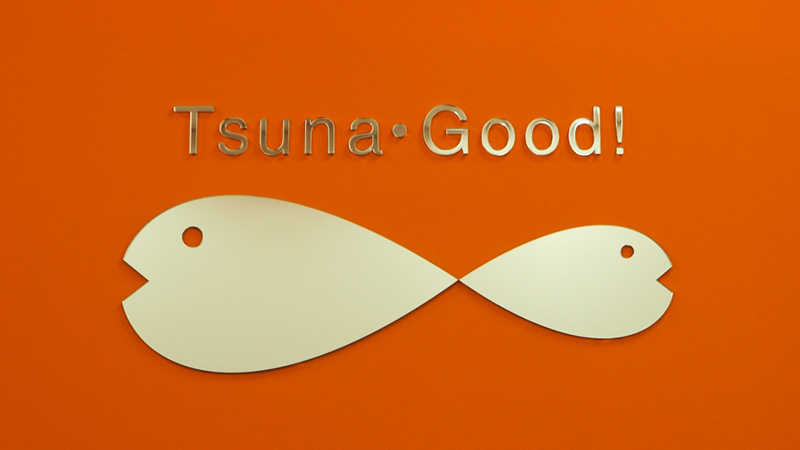従業員にとって満足度の高い休暇制度を作ることは、生産性の向上やメンタルヘルス対策などに繋がるため、多くの企業が取り組むべき課題となっています。
株式会社ツナグ・ソリューションズ(以下、ツナグ・ソリューションズ)ではこれらの課題に対し、ユニークな特別休暇をいくつも設けることで問題を解決している企業。
前編では主に「勉強休暇」について紹介しましたが、後編は「カルチャー&エンタメ半休」を中心に特別休暇のメリットについてご紹介します。
前編はこちら⇒
勉強休暇で社員が資格取得! 株式会社ツナグ・ソリューションズ【前編】
<目次>
・休暇報告でコミュニケーションアップ
・休暇前の引き継ぎが属人化を防止
・半休取得日までの逆算でパフォーマンスが向上
・リーダーの率先取得で休暇制度が定着
休暇報告でコミュニケーションアップ

採用推進部チームリーダー 中西理子氏
中西氏は「カルチャー&エンタメ半休」を昨年取得しました。目的は人気アイドルグループ・嵐のコンサートだったそうです。
同社の「カルチャー&エンタメ半休」は、半期に1度取得できる制度で、土日にはない、平日の街の空気を感じてほしいという意図もあり、通常の休暇では得られない特別感があるとのこと。
映画館や美術館が空いているのも嬉しいポイントと中西氏は話します。

カルチャー&エンタメ半休の報告は義務化されており、貴重な経験を全社員で共有する
同社は東京本社の他に、大阪の関西支社、仙台の東北支社、名古屋の東海支社がありますが、「カルチャー&エンタメ半休」での休暇後は社内ブログ「ツナログ」で報告する義務があります。
この「ツナログ」のコメントを通じて普段顔を合わせない他拠点の社員とのコミュニケーションにもなっているそうです。本文・コメント共に、多くの人の目に触れる文章を書く訓練にもなっているのかもしれません。
休暇前の引き継ぎが属人化を防止

ところで、会社制度とはいえ、社員の休暇が増えることによる業務への支障はないのでしょうか。休んだ人の仕事は他の人がせねばならず、いざ代わろうとしても本人にしかわからないことが多々ありそうに思えます。
しかし、それこそがツナグ・ソリューションズの狙い。
特別休暇がたびたび利用されるということは、業務の引き継ぎも頻繁に行なわれるということ。引き継ぎの度に、情報やノウハウが共有され、属人的になっている業務を減少させる効果があります。
業務やクライアントへの理解が個人でなくチーム全体で深まり、突発的な欠員があってもサービスのクオリティを保つことが可能となります。
特別休暇には、個人のインプットを促して仕事力を向上させる効果に加え、業務の属人化を防ぎ、全員で働けるチームを作る効果もあるのです。
半休取得日までの逆算でパフォーマンスが向上
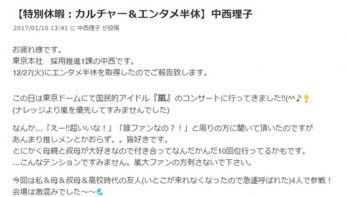
実際の報告画面。社内ブログ「ツナログ」で共有
特別な休暇があることで仕事に対するモチベーションが飛躍的に向上し、作業効率がアップすることも。嵐のコンサートに行く直前の中西氏の仕事ぶりについて、鈴木氏は「いつも以上にすごいスピード感だったよね」と言って笑っていました。
「カルチャー&エンタメ半休」は取得日の3日前までに決裁を取る決まりですが、社員たちは月ごとにお互いの予定を確認し、同時取得にならないよう調整しています。
これは業務を滞らせないこと以外にも、インプットされる情報に多様性をもたせる狙いもあるようです。
リーダーの率先取得で休暇制度が定着
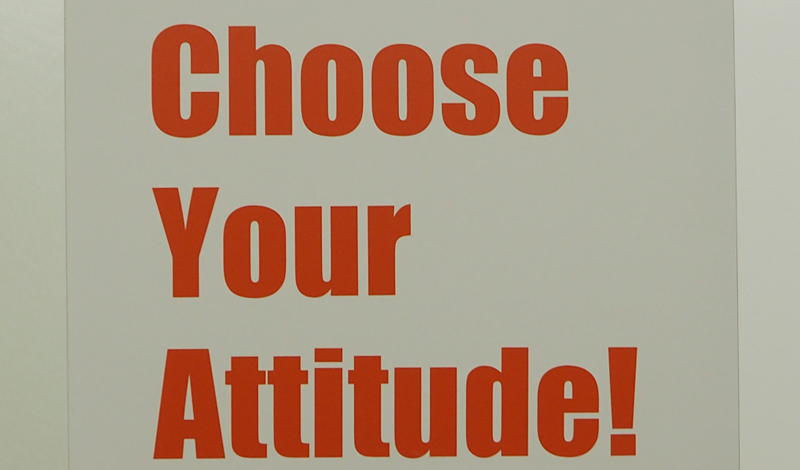
オフィスのドアにはchoose your attitude!(態度を選ぶ)の文字
創業当時からある「カルチャー&エンタメ半休」ですが、新入社員や入社歴の浅い社員は、先輩や上司に気を遣って取得しづらい雰囲気がでてくるのでは、と懸念されていたようです。
しかし、リーダーたちが率先して休暇を取るようにした結果、部署全体でも取得しやすい雰囲気が作られ、実際に昨年の取得率は9割を超えました。
最後に、休暇制度の今後の課題について質問すると、「時代の流れと共に必要なものは変わっていくので、常にブラッシュアップし続けることが必要」という回答でした。現場の声を吸い上げて協議することで、「休暇という仕事」はこれからも進化していくのでしょう。
休暇制度は使い方次第で、単なる個人の休養ではなく、業務の属人化を防いだり、コミュニケーションを活発にしたりと、企業にとってさまざまなメリットを生み出すことができるようです。